NEWS
【2025年最新版】専任宅地建物取引士が退職・不足した場合の対応と実務リスク|宅建業法(第31条の3)・2週間以内補充のポイント
2020/01/07
(最終更新日:2025/10/13)
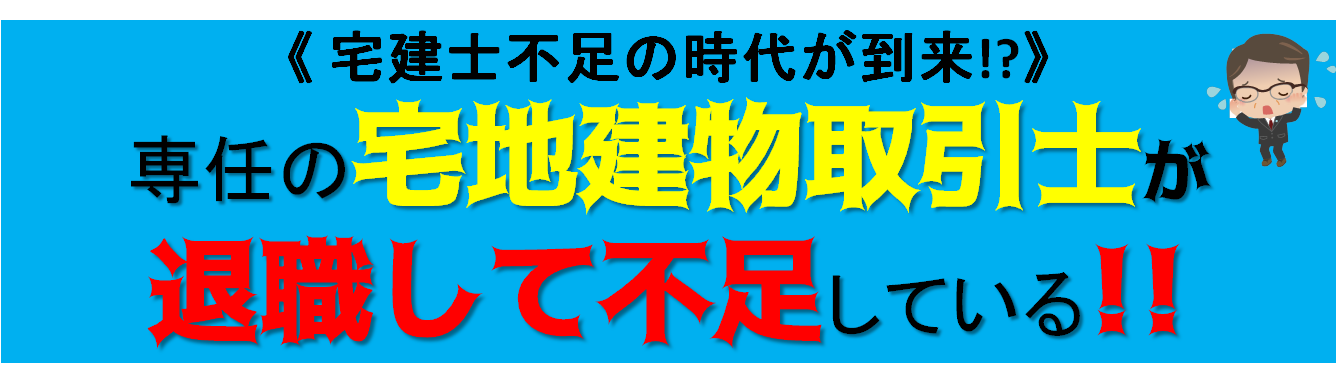
― 宅建業法第31条の3/施行規則15条の5の3対応:欠員発生時は「2週間以内の補充」+「30日以内の変更届」―
(監修:RESUS社会保険労務士事務所/社会保険労務士・宅地建物取引士 山田雅人)
はじめに|専任の宅建士が退職したら「事業停止リスク」
宅地建物取引業法では、事業所ごとに専任の宅地建物取引士(以下、専任宅建士)を一定数以上設置することが義務付けられています。専任宅建士が退職・休職等で欠けた場合、2週間以内に補充しなければ業務停止処分等の行政処分の対象となるおそれがあります。
2025年現在、人手不足・採用難により「専任者が1名欠けたまま補充できない」状況が増えています。本記事は、最新の宅建業法(第31条の3)および自治体運用を踏まえ、リスクと現実的な対策を整理します。
第1章 専任宅地建物取引士の設置義務とは
1. 設置基準(宅建業法第31条の3)
宅建業者は、
「宅地建物取引業に従事する者について5分の1以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない」
と定められています(施行規則15条の5の3)。
たとえば宅建業に従事する社員が10人なら、2名以上の専任宅建士が必要です。
この割合を下回ると宅建業法違反となり、最悪の場合、免許取消しの可能性もあります。
2. 「専任性」の要件(常勤性・専従性)
専任宅建士には次の要件が求められます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 常勤性 | 当該事務所でフルタイム勤務(一般的に週40時間程度)し、他の事務所・会社に常勤していないこと |
| 専従性 | 当該宅建業務に専念しており、他業務や副業を兼ねていないこと |
| 成年要件 | 成年者(18歳以上)であり、成年被後見人・被保佐人等でないこと |
運用メモ:テレワーク等が普及していますが、常勤・専従の原則は厳格です。遠隔地勤務や兼業は原則不可と解されるため、各自治体へ事前相談のうえ就業実態・連絡体制を整えてください。物理常駐でなくても、営業時間中に確実に対応できる実態が求められます。
第2章 専任宅建士が不足した場合のリスク
1. 補充義務(2週間以内)
専任者が退職・休職等により欠けた場合、 2週間以内に補充 しなければなりません。
2週間を超えると、宅建業法違反として指導・業務停止処分を受ける可能性があります。
この「2週間」は、退職日や専任解除日を起算日として計算します。
2. 行政処分・罰則
| 処分・罰則 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 業務停止処分 | 宅建業法第65条 | 一定期間を定めて営業を停止 |
| 免許取消処分 | 同法第66条第9号 | 改善が見られない場合、免許取消しの可能性 |
| 罰金刑 | 同法第82条第2号 | 100万円以下の罰金 |
実際に都道府県が公表している監督処分一覧では、「専任宅建士の未設置」を理由とした業務停止処分事例が毎年複数確認されています。退職者名を残す等の「名義貸し」は重大な違反(法13条等)。発覚時は免許取消・罰則の対象になり得ます。内部通報で発覚する事例もあり、厳禁です。
第3章 不足時にとるべき現実的な対応策
1. まずは「変更届出」を提出
専任者が退職した場合は、速やかに免許権者(都道府県・国交大臣)へ「変更届出書」を提出します。
届出を怠ると、後の監査や更新時に発覚してトラブルになるため注意が必要です。
2. 補充が間に合わない場合の一時対応
-
✅ 採用活動の証跡(求人票・スカウト履歴・面接記録)を残す
-
✅ 有資格の管理者を専任登録へ切替(要件充足を優先)
-
✅ 内部育成(登録実務講習修了者などを短期育成)を並走
-
✅ 業務量の一時縮小で要件充足(従事者数の見直し)
-
✅ 自治体に事前相談(補充見込みと対応計画を提示)
これらを同時に進めることで、監督官庁への説明責任を果たしやすくなります。
第4章 採用・補充の現実的アプローチ
1. 女性宅建士の活用
近年、宅建士合格者のうち女性比率は 35%超(令和5年度) に達し、年々増加しています。
営業・案内業務だけでなく、内勤・重要事項説明・管理部門などへの登用も増えています。
勤務時間の柔軟化、安全配慮の徹底により、採用市場での優位性を確保できます。
2. シニア・ミドル層の登用
60代でも宅建士として活躍している事例は多数あります。
宅建業の経験を持つ中高年層を再雇用することで、即戦力化が可能です。
厚生労働省の「高年齢者雇用安定助成金」などの活用も検討できます。
3. 資格取得支援制度の整備
社内から宅建士を育成することも有効です。
受験料補助・合格報奨金・勉強会開催など、会社全体で取り組むと合格率が高まります。
なお、資格手当は割増賃金の基礎に含める必要があります(労基法第37条)。未算入は未払賃金リスク。
第5章 違法な「名義貸し」に注意
専任者がいない状態で、退職者の名前をそのまま登録しておく「名義貸し」は重大な違反です。
発覚すると免許取消処分の対象となり、再申請にも制限がかかります。
従業員や元社員からの内部通報で発覚するケースも多く、極めてリスクが高い行為です。
FAQ(よくある質問)
Q1. 専任宅建士が欠けたら、いつまでに補充が必要ですか?
A. 欠員発生日を起算として2週間以内に補充が必要です。補充後は30日以内に免許権者へ変更届を提出します。
Q2. 「従事者数」の数え方は?非常勤・アルバイトは含みますか?
A. 「宅地建物取引業に従事する者」には、雇用形態に関わらず実際に従事する者が含まれるのが原則です。従事実態に応じて算定します。
Q3. テレワーク中心でも専任(常勤・専従)と認められますか?
A. 原則は厳格運用です。営業時間中に確実に対応できる実態が求められ、遠隔地勤務や兼業は原則不可と解されます。判断は自治体の運用に左右されるため事前相談を推奨します。
Q4. 名義貸しと見なされる典型は?
A. 退職者名を残す・実態なく登録だけ維持する等です。重大違反で、取消・罰則の対象となり得ます。
Q5. 補充が間に合わないときの最低限の対応は?
A. 採用活動の証跡を残しつつ、要件を満たす人材への専任切替、内部育成、業務量の一時調整、自治体への事前相談を並行します。
第6章 まとめ|“採る”より“辞めさせない”が最大の対策
専任宅建士の確保は、不動産業を継続するための必須要件です。
補充・採用活動に力を入れることはもちろん、
「辞めない職場づくり」こそ最も重要なリスク対策 です。
労働時間の適正化、給与制度の見直し、パワハラ・カスハラ対策など、
職場環境の整備が結果的に宅建士確保の最短ルートになります。
専任宅建士不足の点検・相談はこちら
-
宅建士の退職・不足への対応方針を整理したい
-
監督処分を受けるリスクを回避したい
-
採用戦略・資格者育成を含めた相談をしたい
関連記事
【記事監修】RESUS社会保険労務士事務所/山田雅人(宅地建物取引士・社会保険労務士)
大企業・上場企業を中心に10年にわたり全国500社以上の人事担当と面談、100社以上の社宅制度導入・見直し・廃止に携わった経験を活かし、不動産仲介業者に向けた事務代行サービスと、不動産に特化した社労士として人材不足解消に向けた中小企業の採用コンサルティング業務を得意とし、事業主・従業員双方にメリットの高い制度設計など中小企業の働きやすい職場に向けた取組を支援しています。