NEWS
宅建試験の合格祝い金|支給時の注意点と税金・社会保険料【2026年最新版】
2019/11/26
(最終更新日:2026/01/28)
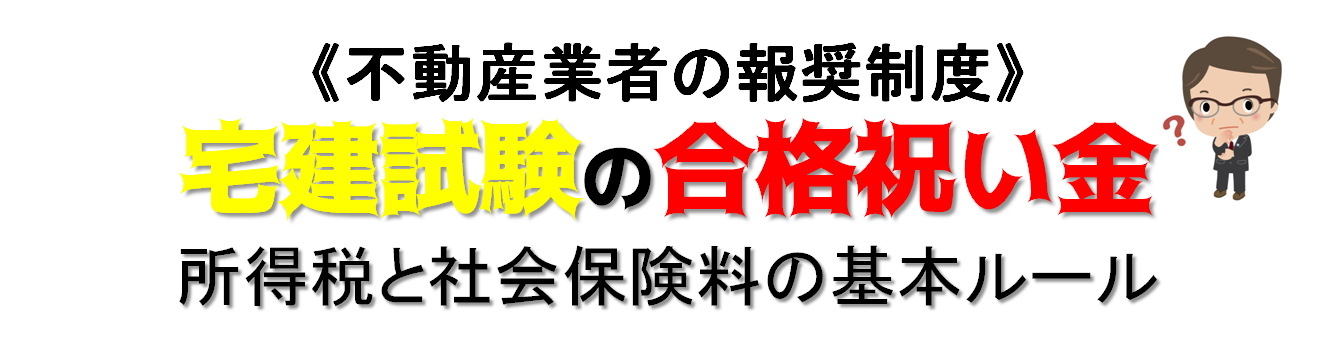
宅建合格祝い金とは?宅建合格祝い金の税金・社会保険料はどうなる?
毎年11月は宅地建物取引士(宅建士)試験の合格発表シーズン。
従業員の資格取得を後押しするために「合格祝い金(報奨金)」を支給する会社も少なくありません。
不動産会社にとって宅建士は事業継続に不可欠な国家資格であり、人材育成・確保の観点から合格者に報奨金を出すことは有効なモチベーション策です。
しかし、この「祝い金」には所得税・社会保険料の課税関係が発生するため注意が必要です。
宅建合格祝い金と所得税の扱い
原則として、会社から支給される金銭や経済的利益はすべて課税対象です。
ただし、国税庁通達(36-29の2)では次のような場合、非課税扱いが認められています。
-
会社の業務に直接必要な技術や知識を習得させるための費用
-
必要な免許・資格を取得させるための研修会や講習会費用
-
大学等での講義受講費用
つまり、受験料や講習費用など「実費補助型」支給は非課税とされます。
一方、「合格祝い金」という形でインセンティブを加算する場合は、実費を大きく超えると課税対象となる可能性が高いため、数万円程度に抑えるのが安全です。
就業規則などに明記しておくことで合理性の説明もしやすくなります。
社会保険料との関係
社会保険(健康保険・厚生年金)では、「報酬」とは労働の対価として支給されるすべてのものを指します。
宅建合格祝い金が「労働の対価」かどうかで判断が分かれますが、以下の整理が重要です。
-
教育費用補助型(受験料・講習料の実費負担) → 報酬に含まれず、社会保険料の対象外
-
合格祝い金(報奨金) → 原則「賞与」とみなされ、社会保険料の対象
ただし、臨時かつ恩恵的に支給される少額の祝い金は、実務上「報酬外」として処理されるケースも見られます。
一方で、日本年金機構の疑義照会では「合格祝い金は賞与に含まれる」との判断が示されており、調査で追及されるリスクはゼロではありません。
労働保険(労災・雇用保険)については「奨励金」に該当しないため、賃金総額に含める必要はありません。
教育訓練給付制度の活用
2019年10月から「特定一般教育訓練給付制度」が始まり、宅建試験も対象に含まれています。
受講料の 最大40%が雇用保険から支給 され、在職中の従業員も一定の要件を満たせば利用可能です。
企業側で祝い金を支給するだけでなく、こうした公的制度を周知・活用することで、従業員の負担軽減と資格取得促進につながります。
実務上の注意点とまとめ
-
宅建合格祝い金は原則「課税」「賞与扱い」となる
-
実費補助型であれば非課税・社会保険料対象外
-
数万円程度なら実務上「非課税扱い」で処理している会社も多い
-
高額支給や規則の未整備は、年金事務所・税務署からの追及リスクあり
-
公的制度(教育訓練給付)を併用すると負担軽減が可能
期待した成果を褒め称えることは重要ですが、税務・社会保険料の取扱いを誤ると、後に追加徴収や指摘を受けるリスクがあります。
祝い金の支給額や規則整備を事前に検討し、健全な制度運営で従業員の資格取得を支援することが大切です。
▶不動産仲介業者向け接客研修・接遇マニュアル作成(売上アップにつながる)
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 宅建合格祝い金はいくらまでなら非課税ですか?
A. 法律で具体的な上限は定められていません。実務上は 数万円程度(例:3〜5万円) であれば「教育費用の補助」として非課税扱いされるケースが多いです。ただし、高額になると「報奨金」と判断され課税対象になる可能性が高まります。
Q2. 宅建合格祝い金は社会保険料の対象になりますか?
A. 報奨金型の場合は原則「賞与扱い」となり、社会保険料が発生します。実務上少額なら除外されるケースもありますが、リスク回避には就業規則に「祝い金は任意的・恩恵的支給である」旨を明記するのが望ましいです。
Q3. 教育訓練給付金と祝い金を併用できますか?
A. はい。教育訓練給付金は雇用保険から本人に支給されるため、会社の祝い金制度と併用可能です。実務上も、企業の支援制度と給付制度を組み合わせて受給しているケースがあります。
Q4. 宅建の合格祝い金は経費にできますか?
A. はい。宅建士は不動産会社に必須の資格であり、従業員の資格取得は事業活動に直結します。そのため、祝い金が適正な額であれば 福利厚生費や研修費として経費計上可能です。ただし、実費を大きく超える高額支給は「給与」として処理される可能性があります。
Q5. 宅建合格祝い金と資格手当は何が違うのですか?
A.
-
祝い金:合格時に一度だけ支給(臨時的・恩恵的)
-
資格手当:資格保有中は毎月支給(継続的・労働の対価)
資格手当は給与の一部であるため、所得税・社会保険料の対象になります。
Q6. 宅建合格祝い金を支給するとき、税金を会社が負担できますか?
A. 可能です。たとえば「源泉徴収税額を考慮して上乗せ支給」することで、従業員が手取り満額を受け取れるように設計できます。ただし、税務署から「過大な福利厚生」と指摘されないよう、支給額と規則の合理性を説明できるようにしておきましょう。
Q7. 宅建合格祝い金を就業規則に書く必要はありますか?
A. 推奨されます。規則に明記しない場合でも任意支給は可能ですが、規則に記載しておくことで
-
課税・社保の扱いの合理性を説明できる
-
従業員間で不公平感を避けられる
-
調査対応で「任意・恩恵的支給」であることを証明できる
といったメリットがあります。
Q8. 宅建以外の資格合格祝い金も同じ扱いですか?
A. 基本的には同様です。
会社の事業に直接必要な資格(例:建築士、マンション管理士など)については「実費補助型」なら非課税扱いされやすく、祝い金型は課税対象になりやすいという整理になります。
Q9. 宅建合格祝い金は労働保険(雇用保険・労災保険)の対象になりますか?
A. 原則として 奨励金は労働の対価に該当せず、労働保険の賃金総額に含める必要はありません。
ただし、毎月の資格手当のように継続支給される場合は算入対象になります。
【記事監修】RESUS社会保険労務士事務所/山田雅人(宅地建物取引士・社会保険労務士)
大企業・上場企業を中心に10年にわたり全国500社以上の人事担当と面談、100社以上の社宅制度導入・見直し・廃止に携わった経験を活かし、不動産仲介業者に向けた事務代行サービスの提供、不動産業専門に特化した社労士として不動産業者の働き方改革を支援しています。
不動産会社の福利厚生制度と労務管理のご相談ならお気軽にお問合せ下さい