NEWS
借り上げ社宅の家賃付帯サービスと課税・社会保険料の取扱い【2026年最新版】
2019/10/16
(最終更新日:2026/01/28)
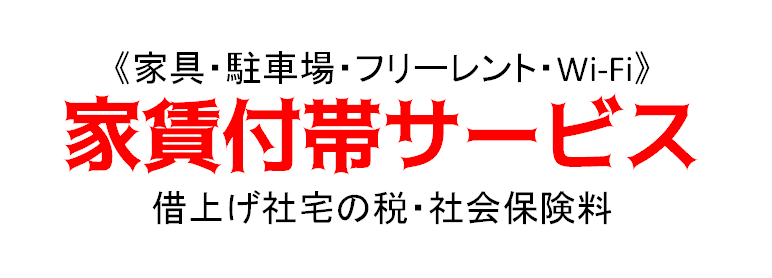
借り上げ社宅の家賃付帯サービスと課税・社会保険料の関係
家具付き賃貸やインターネット無料など、サービス付き賃貸物件は近年増加しています。会社が借り上げて従業員に社宅として貸与する場合、賃料に含まれる付帯サービスをどう課税・社会保険料に反映するかが問題になります。誤った処理は税務署や年金事務所からの指摘対象となるため、基本的なルールを理解しておきましょう。
駐車場が賃料に含まれている場合
-
駐車場代は住居と同じ扱いにはできません(所得税基本通達36-40、36-45)。
-
会社が負担すれば給与課税・社会保険料算定対象になります。
-
賃料に内包されている場合には、相場に基づき駐車場相当額を算出するのが原則ですが、実務上は按分困難で課税していない会社も多くあります。
会社が社宅に付随する駐車場料を負担する場合にはその部分を給与として課税する必要があります。賃料に含まれている場合には社内規程によって駐車場代相当分を定めたり、不動産会社へ近隣相場の聞き取り調査に協力してもらって算出する方法をとっている会社もありますが事実上正確に按分計算することは困難であるため、社宅に駐車場込み(無料)の場合には便宜上課税・社会保険料の徴収を行っていない会社も多くあります。
➡「従業員の負担割合設定については [従業員の社宅利用料はいくら負担させるのが適正?] をご参照ください。」
光熱費(水道代・電気代)が含まれている場合
-
原則として、光熱費は個人負担すべき費用です。会社が負担した場合には給与課税・社会保険料の対象となります。
-
ただし、通達36-26により「光熱費が通常必要な範囲で明確に区分できない場合は課税不要とする取扱い」あり。
-
実務上は按分や規程整備により合理的に処理することが望まれます。
ガス代が賃料に含まれている賃貸物件は無いようですが、水道代は引き込みの関係などによって定額であったり、家賃に含まれているケースもあります。本来水道代や電気代などの光熱費は個人が全額を負担すべき性質のものとされ、会社がその負担を行った場合には個人の給与所得として課税、社会保険法上も標準報酬月額に含まれるものと扱い徴収する必要があります。月々の支払分が明確でなく、賃料に内包されており金額が明確でない場合には合理的な方法によって按分計算を行い、適切な額を負担させる必要があります。
➡「通勤手当や在宅勤務手当の見直しと同様に、 [テレワーク規定と費用負担のルール化記事] でも詳しく解説しています。」
フリーレントが付帯されている場合
-
家主との契約で家賃が減額・免除されても、税法・社会保険法上の賃料相当額は別基準です。
-
従業員の自己負担が免除されると、その分は課税・徴収対象となります。
フリーレントは一定期間賃料を減額したり無料にしたりするサービスで、居住用・事業用問わずに見かけることが多くなりました。手持ちに余裕がない借主や初期費用の負担を軽減する代わりに、一定の契約期間に縛りをもうけるなど、長く住んでもらうために工夫されたサービスですが、借上げ社宅がフリーレント期間中であれば入居者も自己負担しなくて問題無いでしょうか。答えは、「NO」です。家主に支払う家賃と税法・社会保険法上の賃料相当額は関連しないため、社宅がフリーレント期間中であっても入居者に一定額を自己負担させなければ課税・社会保険料徴収義務が発生します。入居者にすれば納得いかない気もしますが、やむを得ません。
➡「契約条件や特典と課税関係の整理については [借り上げ社宅制度を導入する際の基本と手順] を参考にしてください。」
家具・家電が含まれている場合
-
備え付け家具は家賃と一体で扱えます。
-
追加設置された家具・家電は給与課税対象となり、減価償却費やリース料相当額を経済的利益として算出する必要があります(所得税法36条)。
-
雇用保険・労災保険では賃金に含めませんが、社会保険料の標準報酬月額算定では「現物給与」として換算対象になります。
住居と一体となっているような備え付けの家具は家賃と区分せず扱って問題ありませんが、入居者誘引のため別途後から備え付けられたような家具(家電)付き物件であれば、本来は従業員・役員の負担で設置する性質のものとなりますのでその価格の部分は案分して給与扱いする必要があります。
なお、転勤者や単身赴任者に対する負担の軽減として、リースした家具等を無償で貸与している会社もありますが、自社で購入した家具等を貸与する場合には定額法によって計算した減価償却費相当額に維持管理費用相当額を加算し見積もった額を経済的利益として給与課税されます。リースの場合にはリース料相当額が経済的利益として扱われ、無償貸与する場合にはその経済的利益に対して課税関係・社会保険料が発生します。(根拠法令:所得税法第36条第1項、第2項)
➡「役員社宅制度における家具・家電の扱いについては [経営者自身が活用する役員社宅制度] をご覧ください。」
雇用保険・労災保険を定める徴収法上は家具等は社宅と同様に、均衡手当を支給しない場合には賃金には含まれないため無視してかまいませんが、社会保険料の現物給与となる範囲はその他の報酬として扱われ「時価」を通貨に換算し、金銭と合算したうえで標準報酬月額の決定を行うこととされていることから、労使協定がある場合にはその額、無い場合には税法上の処理と同等で扱います。社会保険料の現物給与は数年前までほとんど調査に及ぶことがありませんでしたが、最近は調査されることがあるため報酬から除外する際には自己責任で判断しましょう。
インターネット利用料(無料Wi-Fi)が含まれている場合
-
インターネット代は基本的に自己負担と扱われます。
-
賃料に含まれる場合には按分算出して給与課税するのが原則ですが、実務上は金額特定が困難なため課税処理しない会社も多いのが現状です。
最近はダイワリビングなど大手ハウスメーカーの賃貸アパートでもインターネットの無料サービスを始めています。インターネット利用料は業務遂行上の必要経費と認められないこともありませんが、NHKの受信料や町会費同様に自己負担と扱うのがいまのところ一般的なようです。よって、賃料に含まれている場合には規程もしくは実費相当額を案分して経済的利益・現物給与価格を算出するのが適切な処理といえますが、実務上困難なため給与課税処理せずに扱っているところがほとんどです。
➡「従業員の私用スマホやWi-Fi利用のルール化については [BYOD(私用スマホ持ち込み)対策記事] でも解説しています。」
おわりに
社宅契約に付随して賃料に含まれているものは所得税法上も社会保険法上も、「実務上課税するのが困難であるため課税していない」だけであり、過大なものや恒常的なものとなると指摘される恐れがあります。光熱費など生活に必要な費用が「家賃に含む(無料)」となっている場合には、基本を踏まえたうえで例外扱いとするような指針など、簡単でもよいので書面によるルール作りを行い、監督官庁に指摘された際の説明や反論の根拠を備えておくことが必要です。
(重要なポイント)
-
社宅使用料は、従業員が「賃貸料相当額の50%以上」を負担すれば非課税(国税庁FAQ・社保取扱いも同様)。
-
光熱費・家具・通信費などは原則課税対象だが、例外規定あり。
-
実務上課税しない場合は、社内規程や説明資料を整備しておくことがリスク回避に有効。
⇒不明点は必ず税理士・社労士に相談し、自己判断だけで運用しないよう注意しましょう。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 借り上げ社宅の駐車場代は給与課税されますか?
A. はい。駐車場代は住居と同じ扱いにはならず、会社が負担した場合は給与課税・社会保険料算定の対象になります。
Q2. 社宅使用料を半額以上負担すれば非課税ですか?
A. はい。従業員が賃貸料相当額の50%以上を負担していれば、会社負担分は給与課税・社会保険料算定から除外されます。
Q3. 家具付き社宅の家具費用は課税対象ですか?
A. 備え付け家具は賃料と一体で扱えますが、追加設置された家具・家電は課税対象となり、減価償却費やリース料相当額を経済的利益として計算する必要があります。
Q4. 光熱費が家賃に含まれる場合はどう扱いますか?
A. 原則課税ですが、通達36-26により「算定困難で通常必要な範囲」の場合は課税不要とされることがあります。
【記事監修】RESUS社会保険労務士事務所/山田雅人(宅地建物取引士・社会保険労務士)
大企業・上場企業を中心に10年にわたり全国延べ500社以上の人事担当と面談、100社以上の社宅制度導入・見直し・廃止に携わった経験を活かし、不動産に詳しい社労士として企業の福利厚生制度設計を支援しています。
お問い合わせ
当社では借上げ社宅制度の導入のほか、業務アウトソーシング、制度見直しなど、福利厚生制度全般に係るコンサルティング業務を専門で行っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
《関連記事》
➡社宅業務の外部委託を検討するとき(社宅代行会社の導入比較)
➡【ES向上】転勤者支援サービスが取扱累計300件を突破しました!
➡ワークライフバランスの実現!不動産BPOサービス3,000件突破!